|
HOME > �e�N�m�X�g���N�`���[�̉�

�Z�܂��̍\���̂Ȃ��ł��ł��d������̋��x�����߂邱�ƁA����͂��̂܂Z�܂��S�̂̋��x�����߂邱�ƂɂȂ���܂��B�����Ńp�i�\�j�b�N�d�H�ł́A�̗��Ɍ��S�ȓS��g�ݍ��킹���A����܂ňȏ�ɂ���݂����Ȃ����łň��萫�̍����u�e�N�m�r�[���v���J���B�ƓS�̗Z�����A�o�����X�̂Ƃꂽ���Ղȍ\���̂��������܂��B

���ؑ��Z��̎�_ 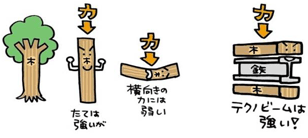
���e�N�m�r�[���͒����d�ɑς����鍂�ϋv���\ 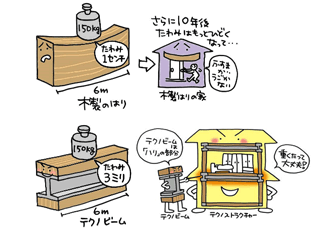
���e�N�m�r�[�����K������n�Z�����߂��� 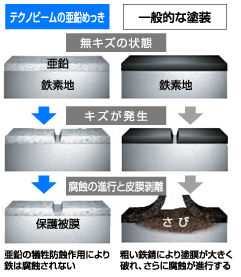
���ڍ����̎�_����������e�N�m�ڍ����� 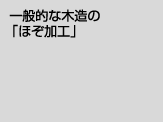
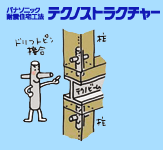
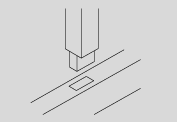

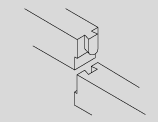

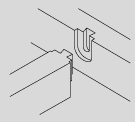

���c���Ђ�т�I�[�v��������� ![�]���̖ؑ��Z��](./img/tec05.gif)
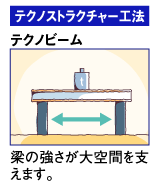

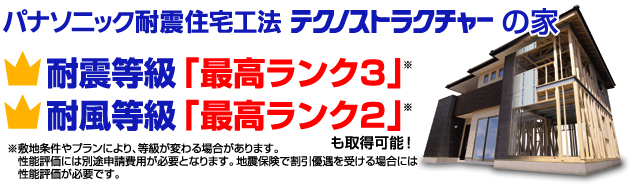
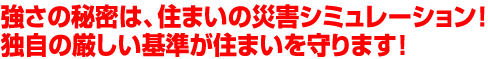
�e�N�m�X�g���N�`���[�H�@�ɂ��Z�܂��́A������̐v�V�X�e���Ƃ����A�ݗ��ؑ��Z��ł͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��A�R���s���[�^�ɂ�鍂�x�ȍ\���v�Z���s�Ȃ��Ă��܂��B�����Ƃ�388�̃`�F�b�N���ڂ�݂��āA�\�����x��O��I�Ɍ����B���q�l�ɂ������n�������Z�܂��ɂ́A���ׂĂ̍��ڂ��N���A�������Ƃ��ؖ�����f�f�������t�����Ă��܂��B

�e�N�m�X�g���N�`���[�̏Z��͖@���Œ�߂�ꂽ���x�������͂邩�Ɍ�������Őv����Ă��܂��B

���z��@���x���i�\���v�Z�͍s��Ȃ��j

�u3�K���ؑ��Z��̍\���v�Ɩh�ΐv�̎�����i���a63�N�j�v�Ȃǂɏ���

�u�ؑ����g�H�@�Z��̋��e���͓x�v�i����20�N�j�v�ɏ���
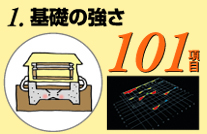
�Ƃ̏d�݁A�n�k�╗�Ȃǂɂ���b�ɂ�����͂��`�F�b�N���܂��B��b�̋��x�����傫�ȗ͂������镔���ɂ͂�葾���S����ꂽ��A�S�̖{���𑝂₵���肵�ċ��x���m�ۂ��܂��B
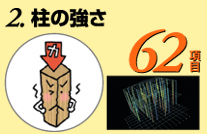
���≮���̏d�݁A�n�k�╗�Ȃǂɂ�蒌�ɂ�����͂��`�F�b�N���܂��B���̋��x���s������ӏ��ɂ͋ߕӂɒ��������ċ��x���m�ۂ��܂��B
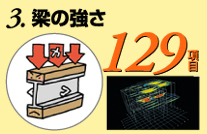
���≮���̏d�݂ɂ����ɂ�����͂��`�F�b�N���܂��B���̋��x���s������ӏ��͗��̔z�u��ύX���ė������S����͂��y����������A�f�ʂ��傫����苭�x�̍�������z�u���܂��B
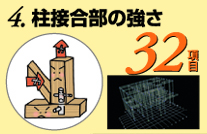
���Ɠy��Ȃǂ��Ȃ�������ɂ�����͂��`�F�b�N���܂��B���ڍ������x�����傫�ȗ͂������镔���ɂ͂��̗͂ɑς�����悤�ɂ���ɐڍ������ŕ⋭���܂��B
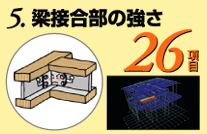
�����Ȃ�������ɂ�����͂��`�F�b�N���܂��B���ڍ������x�����傫�ȗ͂������镔���ɂ͗��̔z�u��ύX���Đڍ��������S����͂��y�������܂��B
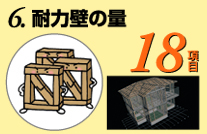
�n��ɉ������ϐ�ʂ╗�̋������l��������ŁA�\���ȗʂ̑ϗ͕ǂ��m�ۂ���Ă��邩�ǂ������`�F�b�N���܂��B���ϗ͕ǂƂ́H�@�n�k��䕗�Ȃǂ̉�����̗͂ɑς��邽�߂ɋ،����Ȃǂ���ꂽ�ǂ̂��Ƃł��B

�ϗ͕ǂ̔z�u�o�����X�̃`�F�b�N�Ɂu�ΐS��0.15�ȉ��v�̌��������p���đS�̓I�ȕǔz�u���`�F�b�N���܂��B���ΐS���Ƃ́H�@�����̏d���̒��S�i�d�S�j�ƌ����̒��S�i���S�j�̂�����\���܂��B�l���傫���قNJ댯�ł��B

�ϗ͕ǂ��\���ȋ��x�����邽�߂ɁA�������Ȃ����ʁE�����ʂȂǂ̐����ʂ��O��I�Ƀ`�F�b�N���܂��B���i�܂��͉����j���x�����傫�ȗ͂������镔���ɂ͂�苭�x�̍�������z�u���܂��B
|